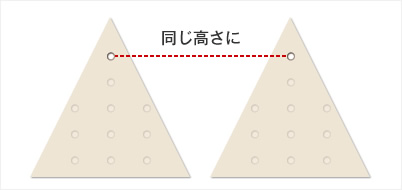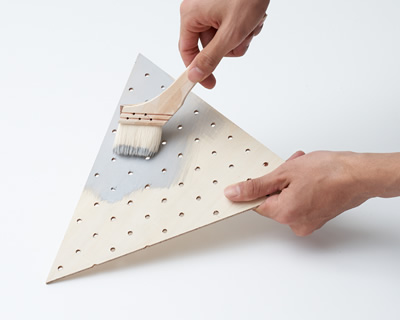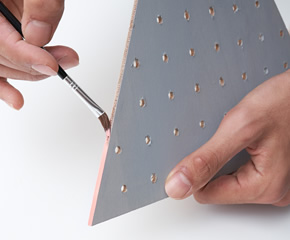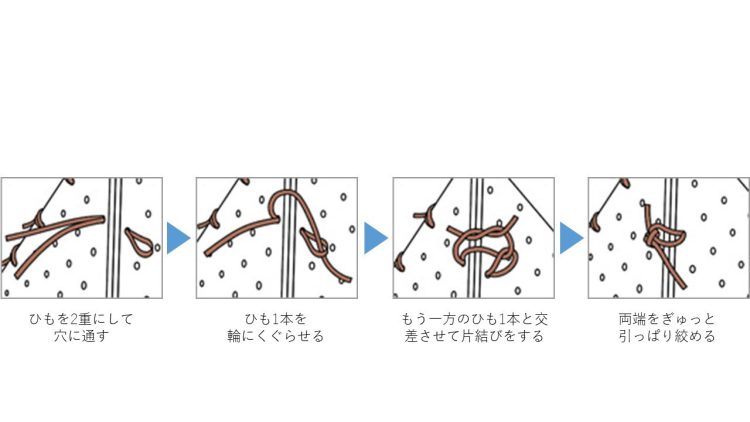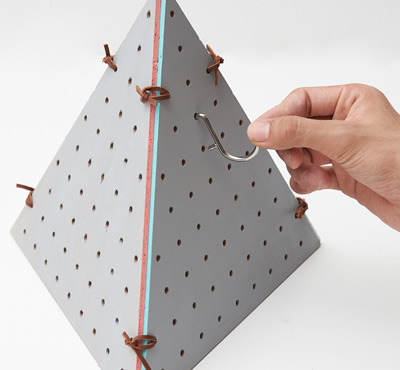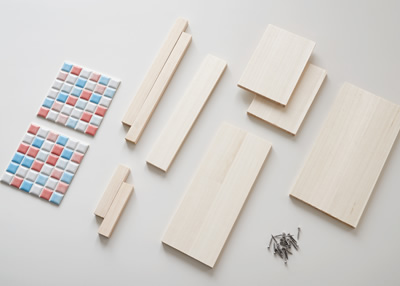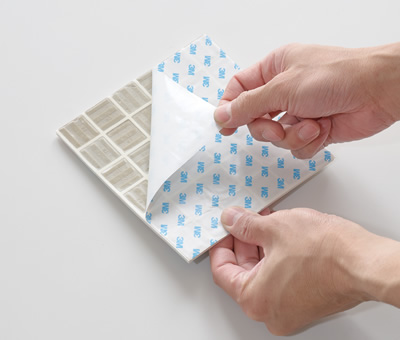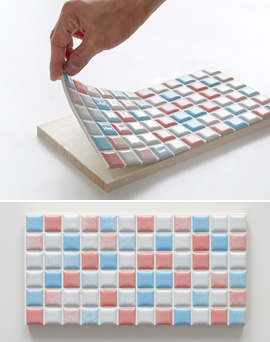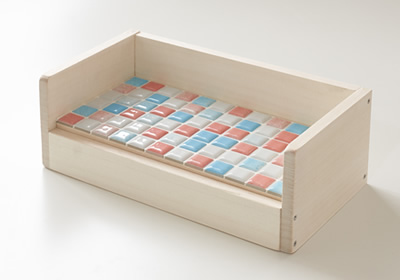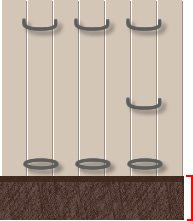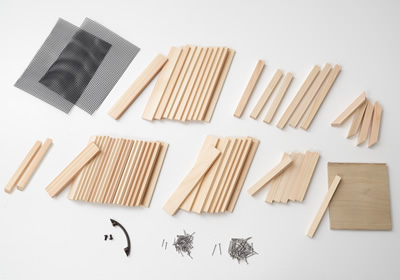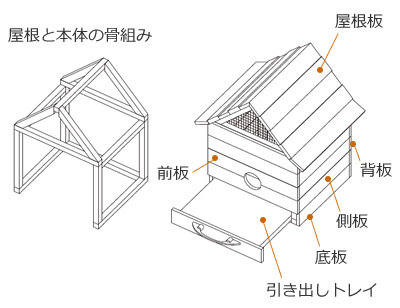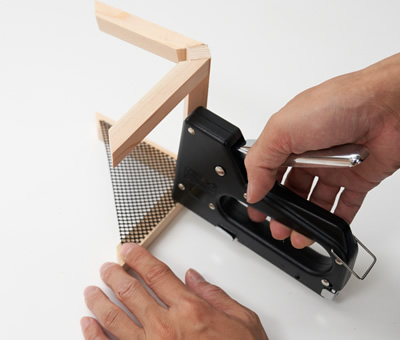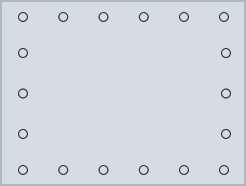木製カッティングボードを おしゃれにリメイク

ミニボトルやステンシルを使って、カッティングボードをおしゃれなインテリアにリメイクしませんか。
黒板塗料を塗れば、家族の伝言ボードにもアレンジできます。
吊り下げても立てかけてもOK。サニタリールームなどにおすすめです。
<用意するもの>
●木製カッティングボード(A、Bの2枚)
●端材
●ミニボトル
●サドルバンド
●麻袋
●転写シール
●黒板塗料
●ブライワックス
●水性塗料
●木工ボンド
●紙やすり

①カッティングボードAを着色する
ブライワックスは古Tシャツの端切れなどに染み込ませて塗ります。

②転写シールを貼る

転写シールを利用すると、手軽にステンシルができます。
好みの文字を選んで半透明シートをていねいにはがしてください。
文字が少しかすれても、いい表情になります。

③ミニボトルを取り付ける

ミニボトルはサドルバンドでネジ留め固定します。
麻袋からカットした端切れを挟み込んでデコレーションします。

④カッティングボードBを着色する
カッティングボードに、黒板塗料を塗ります。
小口部分は紙やすりで整えてから、色違いの塗料で着色するとアクセントになります。


⑤チョーク置きを取り付ける
⑥麻布でポケットをつくる
端材の上に麻布をかぶせてチョーク入れのポケットをつくります。
木工用ボンドで接着します。

⑦出来上がり
Aのミニボトルにはお好みのドライフラワーを挿して、カッティングボードには鮮やかな古切手や絵葉書なども貼って飾りましょう。
黒板塗料を塗ったBは、ご家族の伝言ボードとしても活用できます。